「この制度が目指すべき本質」
飯塚病院 院長 本村 健太
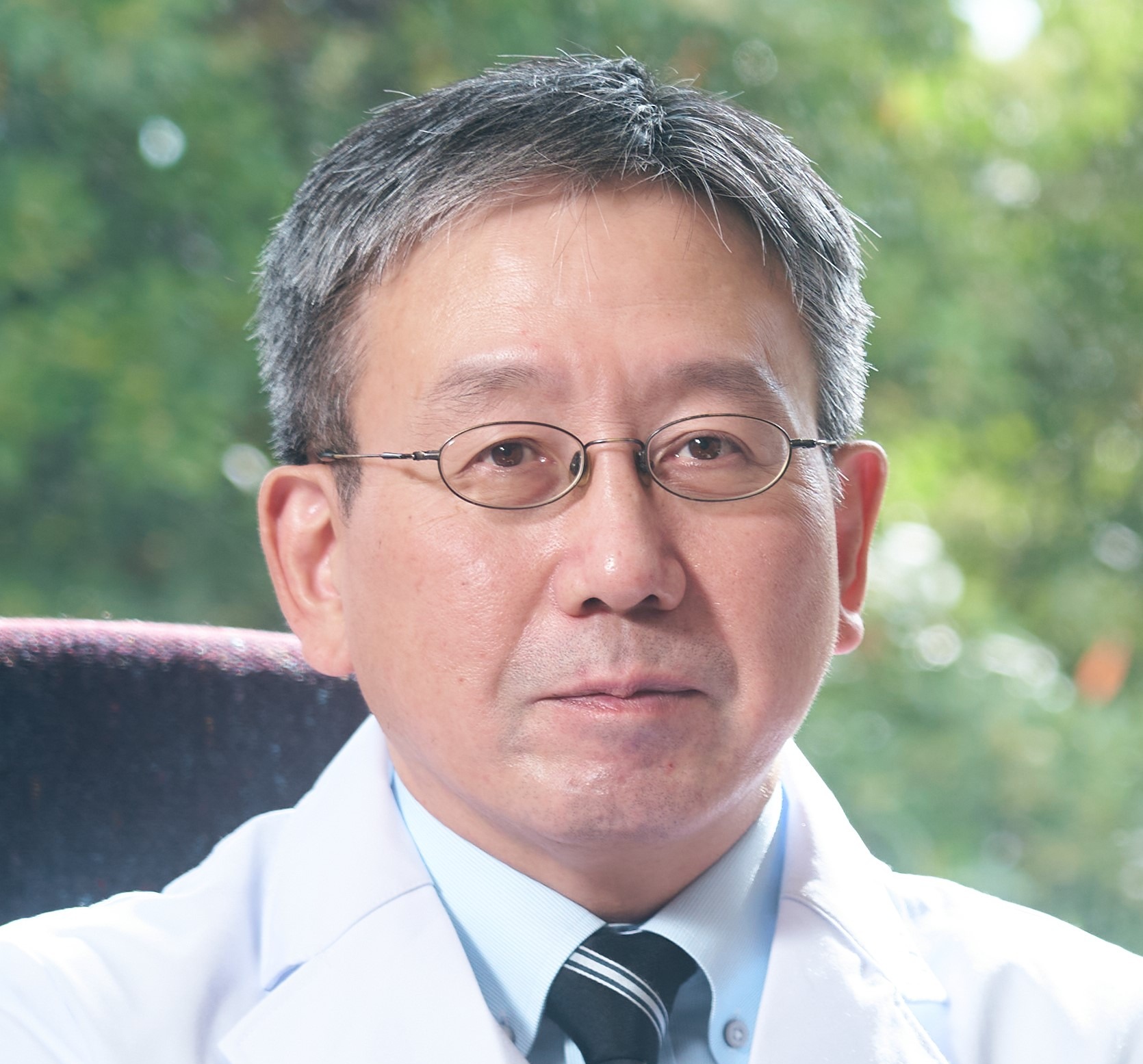
2024年4月から始まった医師の働き方改革も、1年が経ちました。飯塚病院は筑豊地区唯一の救命救急センターであり、救急外来で診療にあたる医師以外にも夜間・休日に院内待機が必要な診療科が数多くあり、常時30人以上の医師が院内にいます。これらは宿日直許可を取得していなかったので、そのままの体制で2024年度に入ると、時間外労働時間の制約から診療縮小を迫られることになるのは必至でした。
この事態に対応するため、人事課に専任担当が配置され、法施行前から制度を綿密に調べて着実に準備を進めていました。まず、医師の勤務状況の確認のために2023年度から貸与スマートフォンによる出退勤の打刻システムを導入し、そのうえで各診療科の「院内待機」中の業務時間発生の記録を作成してもらい、その内容から宿日直許可が得られると思われる診療科については宿日直許可を申請していきました。2023年度の記録から換算するとB/C水準医師が最大40人程度発生することが予想されたため、面接指導のために産業医科大学から2名の常勤の産業医を派遣していただき、また、特任副院長2名と名誉院長に講習を受けて頂いて、想定を超えた面談の発生時の面接指導を担当できる体制としました。
全ての診療科で診療縮小をせずに済んだわけではなく、前々から問題視されていた小児科の救急体制については、飯塚市や医師会、飯塚市立病院も加わった別枠で協議が進められ、小児の夜間休日の1次救急は飯塚病院では対応せず、飯塚市立病院にて行って頂き、救急車と入院症例は飯塚病院小児科の当直医が受けるという体制に代わりました。
また、法制度施行後に院内での調整を要したものとしては救急外来の救急車当番があります。この当番には救急科の医師以外に各診療分野の専攻医が加わっていましたが、専攻医は各自の所属診療科の院内待機にも入るため、時間外労働時間が過剰になってしまう可能性が高くなりました。診療科間の不公平を訴える声もありましたが、会議を招集して協議し、C1水準の専攻医は原則として救急車当番から外す方針としました。
さて、これらのように当院での働き方改革への対応は、いろいろと面倒なこともありましたが、この法制度施行について私が良いと思っている点は産業医による面談の義務づけです。当院の産業医二人は、決して形式的ではなく、疲弊度や睡眠負債などの指標も見ながら真摯に職務を遂行しています。働き方改革の本来の目的は、過労死やバーンアウトの予防ですから、ただ端に時間外労働時間を監視するのではなく、職員の疲弊や異変を早めに察知して対応できる信頼できる仕組みがあることの方が本質的には大切なのだと実感しています。


