「医師の働き方改革と地域医療:『時間』と『豊かさ』と」
公立八女総合病院 企業長 田中 法瑞
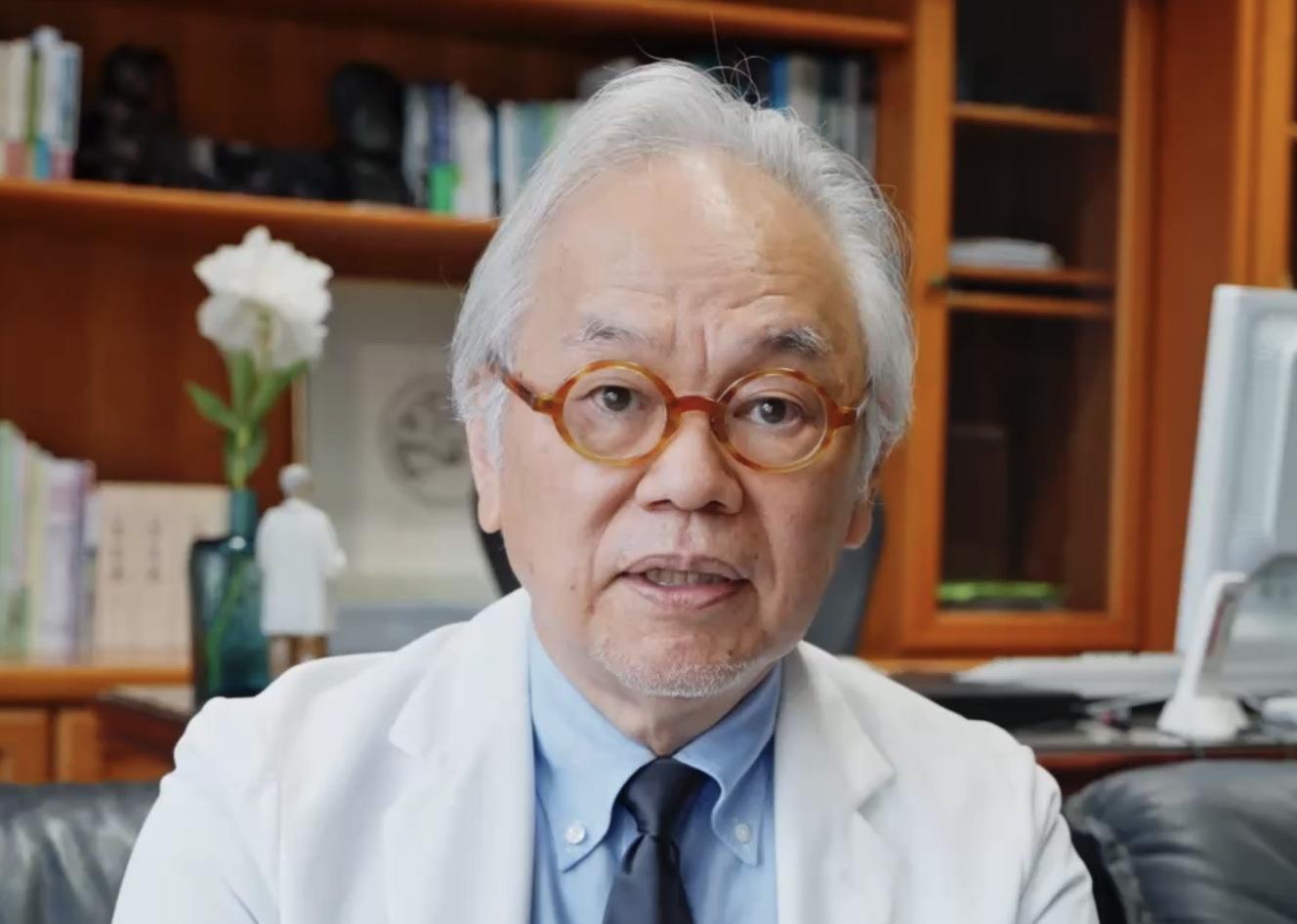
医師の働き方改革は、「時間」の問題を中心に議論されてきた。上限規制、A、B、C水準、「労働と研鑽」も基本的には時間をめぐる問題であり、少しテクニカルな議論になっている気もする。
2024年6月の「新しい地域医療構想等に関する検討会」で「大学病院の医師派遣機能」という資料が発表された。国立大学病院から43,157人、私立大学から15,685人の常勤医が出張病院に派遣されているという。大学病院に勤務する医師約12万人のうち約6万人が地域の医療機関に派遣されていることになる。大学病院の地域医療に対する役割は大きいということだが、大学勤務医の地域の病院での日当直業務の継続が難しくなったことは、地域医療だけでなく大学勤務医にとっても、少なからぬ苦境をもたらしている。働き方改革の目的は「医療の質と安全の確保」であるが、医師の「生活の質」の向上に本当に寄与しているかの評価は十分とは言えない。
医師の給与は、30年前とほぼ変化していない。一方、総合商社5社の平均給与は10年前の1.5陪に増えており、某財閥系商社社員の平均給与は2100万円と公立病院院長の平均給与を上回る。技術革新に対する積極的投資を行わなかった結果、失われた30年と言われる日本経済の停滞をもたらした一方、企業の内部留保は600兆円に膨らんだ。大企業では、給料を更に上げる余力もあるが、赤字の病院は医師の給料を払うのに汲々としている。地域医療を支えている大学勤務医は、外勤が制限され収入減となっている実態がある。大学病院には「開業適齢期」を迎えた医学部定員増の世代がおり、都市部での診療所開業が増加する要因になるかもしれない。働き方改革が医師の偏在を助長するようなことがあれば、地域医療にとって大きな危機となる。「豊かさ」と「時間」の関係には、国民性があるとフランスの経済学者ダニエル・コーエンは言う。フランスでは、より短い労働時間で今までと同じ収入を得ることは、自由な時間を増えることを意味し、それが豊かになることだという。しかし、日本では短い時間で同じ仕事ができるようになっても、余った時間をより多くの収入を得るための労働にあてる。
「豊かさ」と「時間」の考え方には個人差があり、難しい。その中での働き方改革は、価値観を抜きに効率性だけでは議論できない問題を含んでいる。「時間」の議論として単純化するのは、方法論としては致し方ないが、そろそろ働き方改革の結果に対する、勤務医個人の評価が必要な時期に来ていると思う。


